
インクルーシブは教育現場を中心に注目を集めているキーワードです。簡単にいえば、障がいの有無、国籍、年齢などに関係なく認め合い共生するのがインクルーシブです。
しかし多様性を認め合う言葉には他にも、ダイバーシティやノーマライゼーションがあります。これらの違いについて、今さら聞けないと思っている方も多いでしょう。
本記事ではインクルーシブの基礎知識や他の言葉との違い、取り組み事例、課題についてわかりやすく解説します。
Contents
インクルーシブとは?多様性を認め共生できる社会
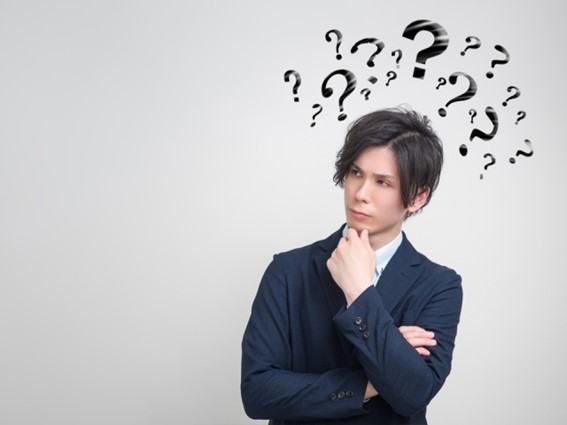
インクルーシブ(inclusive)とは、「包括的」や「すべてを含む」といった意味をあらわす言葉です。その意味から障がいの有無や国籍、肌の色、年齢、性別などに関係なく認め合い共生できる社会をインクルーシブ社会といいます。
他にもインクルーシブ教育やインクルーシブ保育など、教育現場においてよく使われています。
インクルーシブの理念は、1970年代のフランスで誕生しました。教育現場に普及したきっかけは、国連教育科学文化機関(UNESCO)の1992年の「サラマンカ声明」です。サラマンカ声明は、「すべての子どもが一般的な学校で学ぶインクルーシブ教育」が原則であることを宣言するものです。
その後、2006年に障がい者の人権や尊厳を確保し、尊重することを定めた「障害者権利条約」が批准されました。日本は2014年に「障害者権利条約」に批准し、インクルーシブ社会の実現を目指しています。
インクルーシブとダイバーシティとの違い
多様性を認める社会と聞くと、「ダイバーシティ」を思い浮かべる方は多いでしょう。そのため、インクルーシブとダイバーシティの違いがわかりにくいと感じるかもしれません。
ダイバーシティはビジネスにおいてよく使われる言葉で、年齢・性別・国籍・価値観などさまざまなバックグラウンドの人材を受け入れることを意味します。そのためインクルーシブとの違いは、「個性を生かして共生する」という意味を含んでいるかどうかです。
最近では、企業におけるダイバーシティをさらに進めるために「ダイバーシティ&インクルージョン」を合言葉に、インクルーシブな環境の実現を目指すマネジメント手法が注目されています。※インクルージョンはインクルーシブの名詞形
インクルーシブとノーマライゼーションとの違い
ノーマライゼーションとは、障がいの有無に関わらず人類として当たり前の権利を享受し、過ごせる社会を指す言葉です。インクルーシブは障がい者に限定せず、あらゆる人が当たり前の権利を享受し、互いに共生する考え方です。
そのため、インクルーシブとノーマライゼーションは対象者が異なります。ノーマライゼーションは、障がい者や高齢者といった排除されやすい社会的弱者が対象なのに対して、インクルーシブは社会的弱者を含むあらゆる人が対象です。
ノーマライゼーションを発展させた考え方がインクルーシブともいえます。
インクルーシブ社会に向けた国・自治体の取り組み
インクルーシブの概念は、以下のようにさまざまな分野で取り入れられています。
- インクルーシブ教育
- インクルーシブ公園
- インクルーシブ防災
この章では上記の分野において、国や自治体がどのような取り組みをしているのかについて紹介します。
インクルーシブ教育:神奈川県の取り組み
神奈川県のインクルーシブ教育の取り組みは、インクルーシブ教育実践推進校です。具体的には、知的障がいを持つ子どもが高校教育を受ける機会拡大のために、県立高校において知的障がいの生徒を対象に特別募集をおこなう取り組みです。
特別募集の対象者には入学者選抜を面接のみにしたり、高校生活を具体的にイメージできるような事前見学を提供したりと工夫が図られています。
この取り組みを利用し、高校に入学した生徒数の推移は以下のとおりです。
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
| 推進校数 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 定員数 | 63 | 63 | 63 | 294 |
| 入学者数 | 31 | 41 | 53 | 190 |
年々入学者数が増えており、2024年からインクルーシブ教育実践推進校は18校に増える予定です。
インクルーシブ公園:親と一緒に乗れるブランコなど
公園においてもインクルーシブの考え方が取り入れられています。例えば、親と一緒に乗れるブランコやバスケットブランコ、車椅子に乗ったままでも遊べる砂場テーブル、クッション性のある遊具などです。
このような障がいの有無・年齢・性別に関わらず遊べる遊具は、インクルーシブ遊具と呼ばれ、公園に取り入れる自治体が増えています。
インクルーシブ防災:大分県別府市「別府モデル」
東日本大震災では多くの方が亡くなりましたが、障がいを持つ方の死亡率が障がいを持たない方の約2倍になり、改めて障がい者の災害に対するリスクの高さが浮き彫りになりました。
岩手県・宮城県・福島県の被災概要
| 人口 | 死者数 | 死亡率 | |
| 被災3県27市町村全体 | 124万人 | 1.3万人 | 約1% |
| 被災3県の障がい者 | 6.8万人 | 1,400人 | 約2% |
また東日本大震災において高齢者も同様に、死亡率が高くなっています。これらの教訓から、障がい者や高齢者など、あらゆる人が避難できるようなインクルーシブ防災に向けた取り組みがおこなわれています。
とくに大分県別府市の取り組みが有名です。ケアマネージャーやソーシャルワーカー、障がい者などの支援を要する方、自治体や地域の住民が協力し避難する方法を実現しました。この避難方法は「別府モデル」とも呼ばれています。
インクルーシブは企業においても重要視されている

インクルーシブは企業においても取り入れられており、例えば、「ダイバーシティ&インクルージョン」を重要視している企業が増えています。この章では企業と関係の深い、「インクルーシブビジネス」について紹介します。
インクルーシブビジネス
インクルーシブビジネスとは、発展途上国などの貧困層や低所得者を生産・消費・経営に巻き込むことにより、地域の雇用創出や所得向上を目指すビジネスモデルのことです。企業にとっては、事業開始から大きな収益を得られませんが、地域・産業が発展することで一大市場に化ける可能性があります。
つまり、インクルーシブビジネスをおこなうことで、社会全体の発展や社会問題の解決、企業価値の向上が期待できます。
インクルーシブ社会の実現に向けた課題
日本ではインクルーシブ社会の実現に向けた取り組みがおこなわれていますが、現状ではまだまだ実現できたとはいえません。インクルーシブの取り組みには、課題が山積しているためです。
例えばインクルーシブ教育では、すべての子どもを同じ教室で学ぶことが重要視されます。しかし日本では「特別支援教育」という制度のもと、障がい者には専門の教育・支援を提供しています。
2022年に国連の障害者権利委員会より、障がい児を分離する教育制度だとして勧告を受けているものの、手厚いサービスが受けられることや保護者からのニーズがあるため、廃止には至っていません。
本来のインクルーシブ教育を実現するには、教育環境の整備が課題です。加えて、本当に個性を生かせる教育ができるのか、障がいのない子どもがどのように受け入れるのかという懸念もあります。
ビジネスにおいてもインクルーシブの考え方を取り入れよう
インクルーシブは、多様性を認め合い共生を目指す社会のことです。国内でも多くの取り組みがおこなわれているものの、環境整備や人材不足などの課題があります。
これらの実現のためには、国・自治体だけでは困難で、企業においても役割を果たすことが求められています。例えば、ユニバーサルデザインにより障がいの有無や年齢、性別に関係なく使えるインクルーシブ遊具が良い例です。
企業価値を高めるために、ビジネスにおいてもインクルーシブの考え方を取り入れてみてはいかがでしょうか。
